値入率と粗利益率の違いをわかりやすく解説|ロスを見込んだ売価設定をして、しっかり利益を出しましょう!
ちゃんと値入率を計算して売価設定してるのに、思っているような粗利益(率)が確保できない…
会社で粗利益(率)の予算があるけど…、じつは粗利益率と値入率の違いもよくわかっていない。でも、いまさら恥ずかしくて人に聞けないな…
こんな疑問や悩みにお答えします。
本記事の内容
- 値入れ率と粗利益率の違いをわかりやすく解説
- ロスを見込んだ売価設定をして、しっかり利益を出しましょう!という話
本記事を書いている僕は、青果小売業歴25年以上の青果バイヤーです。
そんな僕が「値入れ率と粗利益率の違い」についてわかりやすく解説し、さらに「売価設定をするためには、ロスを見込むことが重要ですよ」ということについてお話しします。
本記事を読むことでスッキリ解決しますので、参考にしていただければと思います。
目次
値入れ率と粗利益率の違いをわかりやすく解説
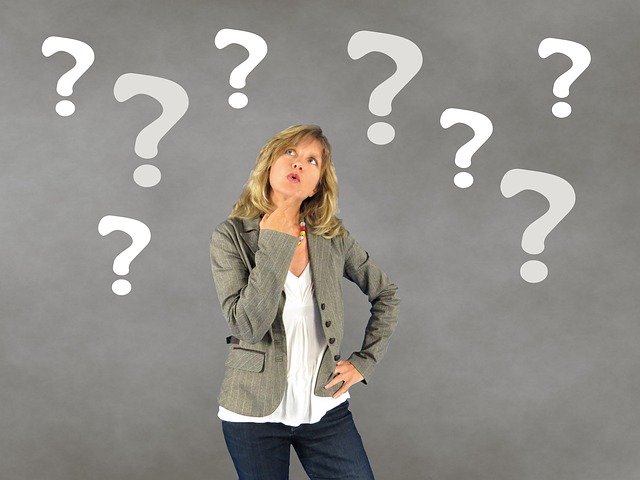
さっそく、値入率と粗利益率の違いについて解説していきます。
値入率とは
売価は「原価に対して、確保したい値入率(値入率分の金額)を乗せる」ことによって決めますが、その計算式は以下の通りです。
- 売価=原価÷(1-値入率)
値入率というのは、この「売価の中に占める、利益のパーセンテージ(割合)」のことで、計算式は以下の通りです。
- 値入率=利益(売価―原価)÷売価×100
たとえば「原価65円で売価100円の場合の値入率はいくら?」であれば、
売価100円-原価65円=利益35円
利益35円÷売価100円=0.35
0.35×100=35%
ということで、値入率は35%になります。
粗利益率とは
粗利益率は「売上高に対する粗利益の割合」のことです。つまり「売上の中に占める利益の割合」のことですが、計算式は以下の通りです。
- 粗利益率=粗利益÷売上高×100(%)
たとえば「1ヶ月の売上高が10,000,000円で粗利益高が3,200,000円だとすると、粗利益は?」だとすると、粗利益率の計算は以下のようになります。
3,200,000円÷10,000,000=0.32
(これに100を掛けるとで%で表すことができるので)
0.32×100=32
つまり、粗利益率は32%になります。
粗利益率は1つの商品に対しても考えられる
わかりやすいように値入れ率の解説と同じ金額で解説します。「売価(売上)100円 原価65円 利益35円」であれば、
35円(利益)÷100円(売価)×100(%)=35
粗利益率は35%になります。
粗利益率は「どれだけ儲けることが出来ているかの目安」で、小売業(商売の世界)で働いていく上で把握することは必須
値入率と粗利益率の違い
値入率と粗利益率の違いですが、上記の計算式を見ると「意味は同じでは?」と思いますよね。
でも全く違います。
簡単に説明すると以下の通りです。
- 値入率→売価設定をした時点での、売価の中に占める利益の割合
- 粗利益率→(一定期間の商売がキリがついた時点での)売上高の中に占める粗利益高の割合
※何が違うのか?:ロスが含まれているかいないか
100%全部売り切ることができれば「値入率=粗利益率」になりますが、これは現実として取らぬ狸の皮算用で、実際には
・商品の廃棄ロス ・値引きロス ・売価変更ミスによるロス ・盗難ロス など
などが少しは出てしまいますからね。
以上が値入率と粗利益率の違いです。
ここで、上記のことから言える「売価設定をする時のポイント」をお話ししようと思います。
ロスを見込んだ売価設定をして、しっかり利益を出しましょう!という話
最終的に目標として狙っている粗利益率を確保するためには、どうすればいいのか?
答えは上記でお話ししたようにロスが発生してしまいますので、ロスを見込んだ売価を設定をしていく必要があります。狙った粗利益率を確保するためには、ロスを見込んだ売価設定が必要!ということです。
例えば目標の粗利益率が30%であれば、全ての商品に対しての値入率30%で売価設定をしてしまうと…、そこから多少のロスが発生して最終的な粗利益率は30%にならないです。
そこであらかじめロスを見込んだ上での値入率で売価設定をする必要があるわけです。
「ロスを見込む」といっても「どれくらいのロス率を見込めばいいの?」という疑問が出てくると思いますが、たとえば青果であれば「ロス率5%」と考えて売価設定をすれば問題ないです。
青果で見込むロス率が5%の理由は【ロス率】スーパー青果部門のロス率は何%?【ロス率の計算式も紹介】でお話ししていますが、簡単に解説すると青果では
・青果の平均ロス率は約3.5% ・5%以上のロス率を出していると重症
だからです。
ロスは先程お話ししたように「商品の廃棄ロス」「値引きロス」「売価変更ミスによるロス」「盗難ロス」などさまざまありますので、絶対に何%という答えは正直ないですが、それぞれの部門(業界)の平均で考えていただければと思います。
「青果で粗利益率30%のノルマ(予算)であれば、5%のロスを見込んで値入率35%での売価設定をしておけば、最終的に粗利益率は30%あたりに落ち着いてくれる」
こんな感じです。
ロスを見込んだ売価設定の計算式
ロスを見込んだ売価設定の計算式ですが、たとえばロス5%を含めた値入れ率で計算する場合は以下の通りです。
売価=原価÷{(1-値入率)-0.05 }
ポイントは「-0.05」です。
たとえば30%の粗利益率を確保したいのであれば「原価÷0.7」ですが、ロス5%を含めて35%の値入れ率で売価設定したいので、「-0.05」(つまり5%)を含めておくということですね。つまり「原価÷0.65」です。
この計算方法について「?」な方は【小売業】売価設定で必要な基本計算式【儲けるコツまで丁寧に解説】をご覧いただけたらと思います。
ロス率の計算式
ちなみに、ロス率の計算式は以下の通りです。
ロス率=ロス額÷売上額×100
おわりに

本記事の大まかなポイントをまとめると、
- 値入率 → 売価設定をした時点での、売価の中に占める利益の割合
- 粗利益率 → (一定期間の商売がキリがついた時点での)売上高の中に占める粗利益高の割合
※何が違うのか?:ロスが含まれているかいないか
狙った粗利益率を確保するためには、最初からロスを見込んだ売価設定をしよう!
参考にしていただけると嬉しいです。
